ネットと知的財産権に強い
力新堂法律事務所
BitTorrent(ビットトレント)による著作権侵害の紛争解決(示談)に多数の実績があります。
発信者情報開示請求をうけてプロバイダーから意見照会書が届いた方は、慌てずに当事務所へ相談ください。
相談無料
オンラインで全国対応
ネットワークに詳しい
理系弁護士在籍
腕組みtrim_ITナビ推奨サイズ.png)
(右)弁護士 弁理士 博士(情報学) 伊藤 英明

意見照会書が届いてしまった時の不安(よくある質問)
刑事告訴されるのか?
回答書になんて答えたら良いのか?
個人情報がバレる?

裁判になってしまうのか?
これ1件で終わるのか?
また来るのか?
ネットに書いてあることのどれが正しいの?
一人で悩まずに、すぐにでも我々にご相談ください。
ネットに書かれている情報の中には、明らかに間違っていたり、根拠のない思い込みであったりする情報も多々あります。ご相談に来られた中には、ネットの情報に振り回されて余計に不安を募らせている方も居られました。
我々は多くの方の相談を受け、ビットトレントに紛争を解決してきた経験があります。
やってしまったことは仕方がありません。より納得性の高い解決方法を見つけるためにも、お気軽にご相談ください。

我々にビットトレントの紛争解決を依頼する
3つの理由
Reason.01
同種事案の経験が豊富な弁護士が対応
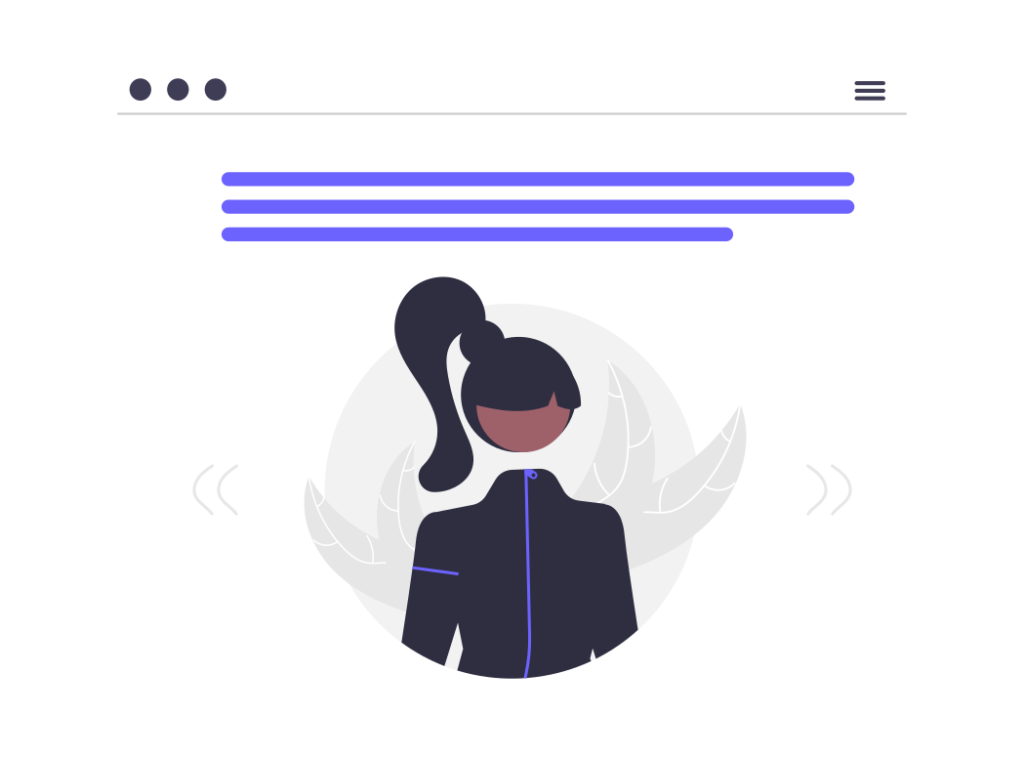
当事務所にはネットワークの応用研究で博士号を取得した弁護士・弁理士が所属しており、BitTorrentをはじめとするネットトラブルの解決に注力しています。また、所内の弁護士間でも事案の経験を他の弁護士と常に共有し合っていますので、安心して事務所にご依頼いただけます。
また、IT技術やネット紛争の裁判例に関して定期的なスキル向上の勉強会も開くことで、依頼者に常に最新の情報をお届けできるよう心がけております。
Reason.02
口コミで全国の依頼者から評価していただくサービス
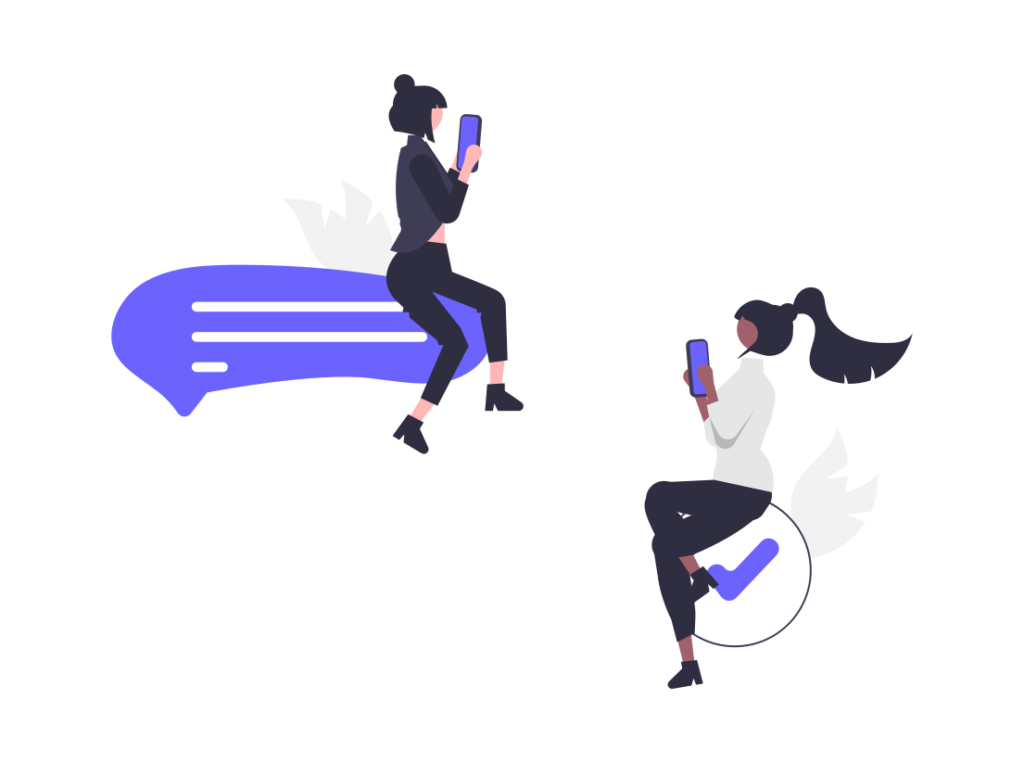
ビットトレントの紛争解決に関する当事務所のサービスについて、アンケート記入や口コミサイトへの投稿などで、多くの依頼者から好評をいただいております。
また、ZoomやFaceTime、LINE動画などを用いたオンライン相談により、北海道から沖縄まで全国の方から相談を頂いています。
もちろん弁護士と対面で相談したい方は、神戸市の事務所までお越しいただくことも歓迎です。
Reason.03
依頼者の不安を理解
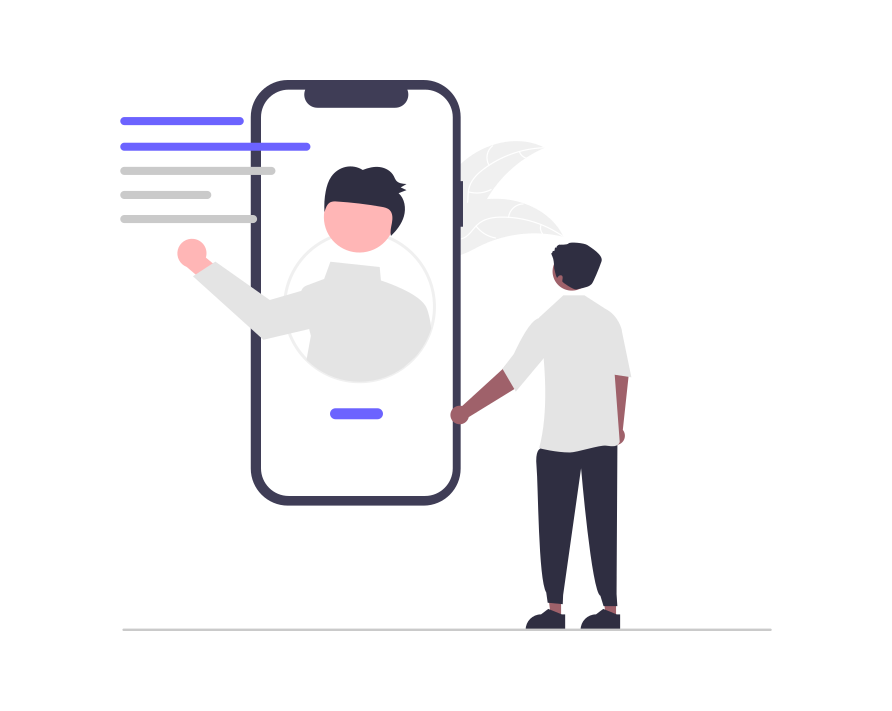
BitTorrentによる権利侵害事案の特徴の一つに、同じ方が複数回の発信者情報開示請求を受けることが比較的多い、という点が挙げられるかと思います。
当事務所では、出来るだけこの不安や負担を解消するお手伝いができるよう弁護士費用や示談交渉の内容など、さまざまな点で工夫をしており、依頼者の方にも喜んでいただいております。


感謝の声多数
お客様の声をご紹介
すべてリモートでの対応でしたが、迅速に対応頂き示談という形になりました。 本当にありがとうございました。
Tanaka Hさん@Google 口コミ
プロバイダーから発信者情報開示請求が郵送されてきたのがきっかけでご相談をさせていただきました。 Torrentソフトの使用で、著作権侵害に関する損害賠償を意図する内容のものでした。 当たり前ですが、このような書類に対応したことがなく、不安になりながらネットの検索で行き着いた力新堂法律事務所様にご相談をさせていただきました。 自分でネットで調べる情報だと、専門的な知識もなく調べれば調べるだけ不安になりましたが、相談させていただいた内容について事例も含めてわかりやすく説明していただきました。 遠方ということもあり、すべてリモートでの対応でしたが、迅速に対応頂き示談という形になりました。 本当にありがとうございました。
適宜、細かな連絡をいただきながら早期に解決まで結びつけていただきました。本当に心より感謝いたします。
Sasaki Yuichiさん@Google口コミ
著作権の件でプロバイダより情報開示請求の問い合わせを受け、不安を抱きながら相談をしたところ、最初の無料相談から親身に相談に乗っていただけその後の正式な依頼後も適宜、細かな連絡をいただきながら早期に解決まで結びつけていただきました。本当に心より感謝いたします。

弁護士紹介

弁護士 茅根 豪
- 兵庫県弁護士会業務委員会等
- 甲南大学知的財産法研究会(事務局)
- 甲南大学法科大学院兼任教授(2020年・企業法務論)
弁護士を志す前は、都心の事業会社で不動産ビジネス等を経験しました(宅建士有資格者)。そのためか不動産関連のご相談を多く受けます。現在は、事務所のメンバーや他業種の方々と一緒に、税務、労務、広告規制、マーケティングなどについての勉強会を開催しています。
弁護士業以外の活動としては、大阪のトレーニングジムで運動機能の改善指導を行ったり、東京で定期開催される政治・経済の勉強会等に参加しています。法律のみならず、広く社会の諸分野についても見聞を拡げていきたいと思っています。
弁護士紹介

弁護士 弁理士 博士(情報学)
伊藤 英明
- 兵庫県弁護士会 民事裁判手続等のIT化検討PT
- 情報ネットワーク法学会
- 兵庫県弁護士会 デジタル・情報対応PT など。
プログラミング歴は20年以上あり、学生時代は商業誌にLinuxの入門記事を連載したり、ゲームを作ったりしていました。修士論文はP2Pネットワークの応用、博士論文はアバターが参加する3次元仮想空間内でのマルチエージェントシミュレーションをテーマにしています。
ネットワークプログラミングやシステム管理、大規模なシステム導入のプロジェクトマネージメント等の経験もありますので、ソフトウェア全般やインターネット上のトラブルについても、技術面での理解に基づくリーガルサービスをご提供します。
よくあるご質問
Q&A
Q
解決までの期間はどれぐらいかかりますか?
A
ビットトレントにより意見照会書が届いた段階で、任意の示談交渉をご依頼いただくケース(多くがここに該当します)では、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度で解決できる場合が多いです。
Q
弁護士費用はいくらぐらいですか?
A
上記の任意の示談交渉では下記の通りです(訴訟は別途の定めによります)。
初回相談
無料
着手金
22万円/件(税込)
報酬金
22万円/件(税込)

BitTorrent(ビットトレント)で発信者情報開示請求を受けた際の対応についての解説
1. BitTorrent(ビットトレント)系のP2Pソフトウェア(ファイル共有ソフトウェア)による著作権侵害について
(1)はじめに
BitTorrent(ビットトレント)は、たとえばOS(オペレーティングシステム)のような大容量のファイルをインターネットで配布/共有する際に、特定の配布サイトに負荷が集中するのを軽減して、素早くファイルを配布/共有することを目的に開発されたP2Pソフトウェアです。
技術的には有意義なBitTorrentによるファイル共有ですが、こうしたBitTorrent(およびμTorrentなど、その亜種)を利用して著作権侵害(著作権者に無断で、著作物である動画等をファイル共有)してしまい、著作権者から利用者のプロバイダーに対して発信者情報開示請求がされるケースが増えています。
侵害をしてしまった人の多くは、プロバイダーから意見照会書が届いたタイミングでこれを知り、どう回答したらよいのか?今後どうなるのか?という部分に不安を感じ、相談に来られています。
そこで以下では、BitTorrentで違法なファイルを共有することの法的な意味とその後の対応について解説します。
(2)BitTorrnetによるファイル共有はどんな権利を侵害しうるのか
「自分はダウンロードだけしているつもりで、アップロードまでしているとは知らなかった」と、相談された方から言われることが多いです。
それは事実なのだと思いますが、とはいえ、対象となるファイルが、誰かの「著作物」であった場合、その著作権者の承諾がない限り、それをダウンロードすることは著作権法上の「複製権侵害」にあたります。
また、ダウンロードした後で、これをアップロードすることは「公衆送信権」/「送信可能化権」などの侵害にあたりえます。
なお、「あたりえます」と微妙な言い方になるのは、ビットトレントのプロトコルの仕様上、必ずしもダウンロードした量と同じだけをアップロードしたことになるとは言い切れないなど、法律の要件にあてはめると、厳密には色々と検証の余地があるように思われるためです(ただし、知財高裁の裁判例(令和3年(ネ)第10074号)によれば、「あたる」ということになりそうです)。
(3)長時間使用していると多額の損害額が推定されうる
著作権侵害の場合、刑事裁判の可能性も無いわけではありませんが、多くの場合は民事裁判が主になると思います。
そして、著作権者が、著作権を侵害した相手に請求できることは2つあります。1つ目は差止請求(たとえば、違法な複製物をこれ以上共有されないように削除しろと請求すること)であり、2つ目は損害賠償請求(金を払えと請求すること)です。
個人がBitTorrentによって著作権侵害をしたような場合、差止めの方は問題とはなりにくく、主には損害賠償請求が問題になります。そして、著作権法114条には損害額の推定規定があり、ざっくり言えば、たくさんの人へアップロード(公衆送信)して共有するほど損害額が高額になりえます。
そのため、自分のPCでビットトレントのソフトウェアを長時間起動しっぱなしにしていた場合、思いがけないほどの多人数へ公衆送信してしまっており、多額の損害額が推定されるリスクが生じえます。
(4)意見照会書受領後の対応
具体的な対応は、意見照会書を受け取った方が、自身の行為を認めるのか、人違いだと争うのかで全く異なってきます。そのため、まずは認めるのか否かをご自身で決めていただく必要があるかと思います。
その後は、認める場合も争う場合も、BitTorrentによる著作権侵害紛争については、通常のWEBやSNS上でなされた著作権侵害紛争とでは、法律上の手続きや技術的観点において、共通する部分と、争点が異なる部分とが生じ得ますので、ご自分であれこれ検索するよりは、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか? 当所でも初回無料でオンライン法律相談が可能です。
(5)おわりに
つい安易な気持ちで違法行為をしてしまった方がプロバイダーから手紙を受け取った時の不安な気持ちは大変なものだと思います。当所へ相談に来られる多くの方は、「ファイル共有ソフトウェアはもう懲り懲りだ」と言われます。
ただ、BitTorrentを含め、P2Pによるファイル共有の実装なり技術自体は良いも悪いもない「ただの道具」ですので、世の中をより良くする便利な使い方も勿論あります(刃物や自動車と同じです)。
当事者となられた方にとっては、今はそんなことを考える余裕はないかもしれませんが、一旦、当該紛争に決着をつけて落ち着いたあとは、便利な道具を正しく使うようにリテラシーを高めていく具体的行動をとることが、次の過ちを防止する上でも大切なことではないかと思います。
2. BitTorrent(ビットトレント)等のファイル共有ソフトウェアで発信者情報開示請求を受けてしまった場合のゴール設定の考え方
(1)忘れた頃に届くプロバイダーから意見照会書
多数ご相談いただいているビットトレント(及びμTorrentなどその互換ソフトウェア)などのファイル共有ソフトウェアによる著作権侵害事件ですが、多くの相談者の方は、違法行為から数ヶ月たって忘れた頃にプロバイダーから意見照会書が届いてびっくりされます。
ただ、意見照会書には通常、「こういう動画共有についての著作権侵害を疑われていますよ」と、画面がキャプチャされた資料も添付されていますので、それを見るとある程度は納得されて、行為自体は争わず、円満な解決を望まれる方がほとんどです。
(2)動画共有の著作権侵害における円満解決とは?
ビットトレントなどのファイル共有ソフトウェアにより違法な動画共有をやってしまった方にとっての、その後のリスクとしては、民事訴訟での損害賠償請求に加え、刑事事件化されるリスクも想定されます。
そこで、この場合の円満な解決策としては、ある程度のお金を払うことで、民事・刑事の責任追求をこれ以上しない、というような内容の「示談書」締結をゴールに設定することが多いです。
早期に示談してしまえば、相手方(著作権者)側の裁判手続きに必要な負担も減りますから、比較的低い金額で示談に応じてくれやすくなる傾向がありますし、ご自身の弁護士費用も安くなるはずです。
また、訴訟手続きには、相手方の氏名、住所等の情報が必要(なので、発信者情報開示請求をする)ですが、弁護士がついた示談交渉であれば、場合によりけりですが、著作権者にご自身の住所などを伝えることなく事件を終わらせられることも多いです(なお、氏名は示談書に記載するのが通常です)。
(3)おわりに
著作権者側が訴訟を前提とした手続きを始めている以上、心当たりがあっても無くても、放置しておいて良いことはおそらく無いと思います。
意見照会書が届いたら、少しでも早めにご相談ください。ZOOMやLINEによるオンライン相談も初回無料でお受けしていますし、相談日時について、我々も可能な限り迅速な対応ができるよう努めています。

3. 知財高裁の裁判例(令和3年(ネ)第10074号)から考える、ビットトレントによる著作権侵害についての侵害者側の対応
(1)はじめに
BitTorrentにより有料動画を共有したとして、著作権侵害を理由に動画の制作会社から発信者情報開示請求を受けたBitTorrentユーザ(X1〜X11)が「原告」として、著作権者である制作会社に対して、「損害賠償債務が存在しない」ことの確認を求めていた裁判について、令和4年4月20日に判決の言い渡しがありました。
この事件、最初は東京地裁に令和2年(ワ)第1573号として係属し、簡単に言えば、原告(BitTorrentユーザ)のうち、X5とX11の二人については原告の勝ち、それ以外の原告については負け、という形で令和3年8月に判決の言い渡しがあったものです。
その後、X2以外の原告と、被告(動画制作会社)が控訴し、その判決が出たことになります。知財高裁の判断内容としては、技術的な観点からの表現の修正や、理由の補足がなされ、また著作権侵害の責任を負うべき期間が短縮されるなどしたものの、大筋としては東京地裁の判断が維持された(一審原告であるBitTorrentユーザのうち、X5とX11以外は負け)と言えるかと思います。
当事務所では、BitTorrent利用による著作権侵害として、プロバイダーから「意見照会書」が届いたがどうしたらよいか、というご相談を多くいただいていますが、その際の対応を考える上で、この裁判例は有意義に思いましたので、詳しめに検討していきたいと思います。
(2)裁判で争われた争点ごとの結論と、実際の相談事例との関連
この事件では、原告・被告とも、ふだんから我々が考え、また依頼者の方からもしばしば受ける質問のヒントになるような争点について争われています。
そこで、以下では、特に大きな3つの争点について、①争点、②裁判所の判断、③当所の相談でよく聞かれることへの影響、という観点で整理します。具体的な争点ごとの詳細は、別な機会での説明を予定しています。
〔争点1〕著作権侵害(行為)の有無
①争点
そもそも、BitTorrent自体はなんら違法性がない仕組みですし、また、民事訴訟は漠然と「なんらかの違法なファイル共有をした」ことを争う場所でもありません。著作権侵害を理由に損害賠償請求をする場合、著作権者は、自分が著作権を有する動画のうち、どの動画について相手方がどのように著作権を侵害したのかを具体的に証明する必要があります。
争点1では、この点について、「本件で問題とされている特定の動画ファイル」を本当に一審原告らが共有(ダウンロード及びアップロード)したのか、具体的な侵害行為の有無について争われました。
②裁判所の判断
この点について東京地裁は、X5とX11については「IPアドレスに係るハッシュは明らかではないので、…ダウンロードしたと認めることはできない。」と認定し、知財高裁もこの判断を維持しました。
意見照会書を受け取った方は、おそらく、プロバイダーからの資料にハッシュ値(データを関数に入れて計算して得られる計算結果の数値。同じデータであれば同じ数値になる。逆も真かはモノによる)が書いてあるかと思います。本件では、裁判所に出された証拠上、X5とX11については、問題とされた特定の動画ファイルと一致すると認定できなかった(ので勝てた)ということかと思います。
一方、X5とX11以外のユーザーについては、東京地裁及び知財高裁とも侵害行為を認定しています。
③当所の相談でよく聞かれることへの影響
実際のところ、BitTorrent系のソフトを使用する際に、細かい動画のタイトルや制作会社を覚えている人は多くはないため、具体的な「その」動画を共有したかは記憶にない、という方は多くおられます。
ただ、本件についての具体的な背景はわからないのですが、判決書を読むかぎり、X5とX11については特殊な事情があったようです。
一般的には、著作権者が、信頼性が確認されたとされるシステムによってBitTorrentのネットワークを利用しているIPアドレスとファイルのハッシュ値を具体的に特定し、これに基づいて発信者情報開示請求をし、その後にプロバイダーから著作権者に対してIPアドレスに対応する契約者の氏名及び住所の開示がされ、後の裁判はそれを前提に進む、というのがよくある流れかと思います。
とはいえ、そもそもIPアドレスは特定の個人に紐づけられているものではなく生成したソケットに紐づくものですし、今後も争点となる余地は多々あるように思います。もしご自身が受け取った意見照会書等に疑問がある場合は、ご相談ください。
〔争点2〕共同不法行為性について
①争点
我々は、通常は自分がしたことの範囲でしか責任を負いません。例えばAさん、Bさんの二人が別々にCさんの権利を侵害した場合、AさんとBさんは、それぞれ別々にCさんに対して損害賠償債務を負う(民法427条の分割債務となる)のが一般的な不法行為の考え方です。
しかし、ある損害の発生について複数の人の行為が直接又は間接に相関連共同している場合など、原則通りだと不公平が生じる場合は、その損害の賠償について、関係者全員に連帯して共同責任を生じさせる規定があります。民法719条には、こうした「共同不法行為」に対する共同責任について規定しています。
共同不法行為が争点となった理由は、BitTorrentに参加するノード(ピア)間で送受信されるデータの単位は、大元の動画データを細かく分割した一部である「ピース」であり、ここのピースだけを見ると「著作物(=思想感情を創作的に表現したもの)」とは言えないんじゃないか、という当然の疑問が生じるためと思われます。
著作権侵害は「著作物」を複製したり、ネット上のオープンな場所に置いたりした場合に問題になるわけですから、BitTorrentにおいてピア間で送受信する「ピース」が著作物でないならば、著作権者は、ある一つのピアが全てのピースを送受信したことを立証できなければ、当該ピアに対応するクライアントを起動していたユーザについて著作権侵害が成立しないことになりえます。
しかし、BitTorrentによるファイル共有について上記の共同不法行為が成立するならば、ある動画ファイルのトラッカーにぶら下がる全てのピアが相互に関連し共同してファイルを共有しているのだから、当該ピアに対応するクライアントを起動していたユーザ全員に対して共同責任を生じさせることができます。
そのため、本件でも共同不法行為の成否やその内容が争われています。
②裁判所の判断
知財高裁は、Torrentのネットワークにおける通信の実情等を認定しつつ、719条1項の共同不法行為の成立を認めました。ただ、共同不法行為で議論されている細かい法律論の中身については特に触れられていません(それが裁判所全般のデフォルトですが)。
③当所の相談でよく聞かれることへの影響
我々の相談者のうち、BitTorrentの仕組みについても調べておられる方で、「動画ファイルの一部しか送っていないのであれば著作権侵害が成立しないのではないか」と質問してこられたケースがありました。
私自身、判決書を読んだだけなので本件の裁判所の認定がどこまで妥当なのかはよくわかりませんが、本件を参照する限り、たとえ動画の一部のみをアップロードした場合にも、著作権侵害は成立すると言う判断がされる可能性が高いということになりそうです。
また、相談者の中には逆にBitTorrentの仕組みを全くわかっておられなくて、「自分が取得したファイルがその後に送信(可能化)していることを知らなかったのだが、それでも責任を負うのか」と質問される方もおられます(こちらの方が多い印象です)。
これについて裁判所は「ファイルをダウンロードした場合、同時に、同ファイルを送信可能化していることについて、認識・理解していたか又は容易に認識し得たのに理解しないでいたものと認められ、少なくとも、本件各ファイルを送信可能化したことについて過失があると認めるのが相当」 という判断を示しています。
〔争点3〕共同不法行為に基づく損害の範囲
①争点
BitTorrent上で動画ファイルを共有することについて、各ピアとなるクライアントを起動させているユーザ間に共同不法行為が成立する場合であっても、共同責任を負うべき期間は、当該ネットワークが発生してから(トラッカーが稼働してから)未来永劫の全ての期間(最大の期間)から、各ピアごとに、起動していた個別の合計時間(最小の期間)まで、大きな幅が考えられます。
しかし、いくら共同不法行為が成立するとしても、そもそもBitTorrentのネットワークに参加する前に他人が侵害した分まで責任を負わされるのは因果関係がなく不当ではないか、とも思われます。
本件でもこの点が争点として争われました(他にも、損害額を推定する際の要素について争われていますが、期間の認定が特に問題になるように思いますので、他の点はここでは省略します)。
②裁判所の判断
結論として、裁判所は、各ユーザがBitTorrentを利用していない時期については因果関係がないとして、BitTorrentの利用前と、利用終了後については責任を負わない旨を判断するとともに、ユーザごとに侵害行為の始期と終期を認定しました。
このうち始期については、言及されている具体的な証拠の内容がわからないのですが、おそらくBitTorrentの使用状況を調査するサービスにおいて、当該ユーザに対応するIPアドレスが特定の動画ファイルに対応づけられて検出された日時のうちのいずれかを使っているのだろうと思います。
一方の終期については、原審の東京地裁では、「各ユーザがプロバイダーから意見照会書を受け取って(本件訴訟の代理人となっている)弁護士に相談した日」と認定したのに対し、知財高裁では、「各ユーザがプロバイダーから意見照会書を受けた日」に訂正されています。
③当所の相談でよく聞かれることへの影響
相談者からは、プロバイダーから割り当てられるIPアドレスが変わることを根拠に反論できないかという質問をうけることがありますが、少なくともプロバイダーから開示された結果に基づいて事実認定がされている限りでは、IPアドレスの割り当てが動的であること自体は問題になりにくいように思います。
むしろ大事なのは、BitTorrentで違法な行為をしてしまったことを自覚したなら、なるべく早く同クライアントの「利用を終了したことの証拠」をつくることかと思います。 訴訟で争う場合はもちろん、示談交渉で和解する場合であっても、あまりに利用期間が短いことを示す証拠があれば、交渉の幅が出てくる可能性があるためです。
上記の証拠作りについても、状況に応じて色々な方法が考えられますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
かなり長くなってしまいましたが、まとめると、
- 侵害行為を否定することは、相手方が立証に失敗しない限り、こちらから積極的な「何か」を証明しないと難しいだろう
- 「BitTorrentの仕組みを知らなかった」は、たぶん認められない
- 著作物の一部の送受信であっても、共同不法行為として著作権侵害が成立しうる
- 賠償責任を負う期間は、各々がBitTorrentの利用を開始した時期から利用を終了した時期まで
- 少しでも責任を負う期間を短縮するためには、早期に利用を終了した証拠を作っておくことで有利になる可能性がある
となります。
我々がBitTorrentの著作権侵害について依頼を受ける際、基本的には、妥当な示談金で収まるのであれば相手方弁護士との交渉を通じて示談するのが、結果的に依頼者の負担軽減につながるケースが多いように感じています。
本件は一審原告が多数いるため一人当たりの具体的な弁護士費用がどうなったのかわかりませんが、通常は、違法な動画共有について裁判で争うのは、費用面に加えて、時間的・精神的な負担も大きいのではないかと思います。また、仮にある訴訟で勝ったとしても、BitTorrentで色々共有していた場合には、別な著作権侵害について別途訴訟を起こされるリスクもあります。
こうしたコストとのトレードオフとして、合理的な範囲での示談ができるようにお手伝いしておりますので、プロバイダーから意見照会書が届いたり、あるいは届く前であっても違法に著作権侵害をしてしまった、という方は、お気軽にご相談ください。不安を解消するための一番良い方法を、一緒に検討させていただきます。
